2010年2 月 1日 (月曜日)
完成度の高いカーフィルムの登場なのか
クルマのウインドに貼るオートフィルムは、プライベート重視機能や紫外線カット、断熱効果によるエアコンの機能向上など多方面にメリットあるのだが、美しく貼れないとか車検にパスしないなどの心配事も少なくなく、貼る気持ちになれないユーザーも少なくなかった。
ところが、こうした心配事を払拭したオートフィルムが登場した。
「3Mスコッチティント・オートフィルム」がそれ。このスコッチティントは、高性能・高品質のフィルム。各メーカーの全車種にあわせた正確なデータに基づき、コンピューターでカットし、パーツ分けしたフィルムで作業時の型取りが不要。リーズナブルな価格で入手できるという。
有害な紫外線から肌を守り、じりじりする夏の車内の暑さを抑えて、快適性を向上させる。スモーク系から、貼っていることが分からない透明でピュアなタイプといろいろ選択できる。たとえばスモーク系のフィルムを選択すれば、車外から見えづらくセキュリティ面でも効果も期待できるし、透明度の高いタイプなら「黒色のフィルムはちょっと」という女性でも抵抗感がない。
エアコンの効き向上率は、温度差なんとマイナス12℃というデータもある。つまり省エネにもなるという理屈だ。スモークタイプのフィルムにも種類があるので、詳細は、この商品を扱っている「タイヤショップショウワ越谷店」(電話048-970-0505)に問い合わせてほしい。
写真は、手をかざし断熱効果を確かめるデモ機で、同店で体験できる。
2010年1 月15日 (金曜日)
第3世代のランフラットタイヤは乗り心地が向上
車両の軽量化と小型化が世界的な規模で加速している自動車業界。
従来当たり前のように積んでいたスペアタイヤは、いつの間にか、補修キットを積むようになり、さらにランフラットタイヤと呼ばれる≪パンクしても走行できるタイヤ≫に近い将来移行する模様。
すでに、アメリカではその動きが始まっている。
現に、トヨタの北米仕様のミニバン「シエナ」に採用されているのは、ブリヂストンの第3世代のランフラットタイヤ「TURANZA EL400RFT」(タイヤサイズはP235/55RF18 99T)。世界初の採用だという。このランフラットタイヤの新門は、熱をコントロールする技術としてタイヤサイド部を冷却するクーリングフィンと発熱を抑制する新サイド補強ゴムを採用したことだという。そのおかげで、たとえパンクした状態で走行しても乗り心地が最小限に抑えられることだ。
この完成度の増した第3世代のランフラットタイヤ、日本仕様車にも遠からず取り入れられる時代が来るだろう。
2010年1 月 1日 (金曜日)
空力特性を高めるホイールキャップ
クルマの燃費をよくするための手段として、現在大まかに3つの手段が考えられる。
エンジンの効率を高めること、車体を軽くすること、それに空力特性を高めることの3つである。
トヨタのハイブリッド高級車SAI(サイ)には2つのアルミホイールが設定されている。18インチと16インチ。そのうちの16インチは、最小回転半径を5.2メートルとワンクラス小さいクルマ並。
実はそれだけではなく、軽量化と空力特性を高める役目をしている。とくに空力特性は樹脂製のフルホイールキャップを付けることで、空力を表わすCD値を0.004ダウンするのに貢献。燃費を高めるのに役立っている。実はこのフルホイールキャップを取り付けることで空力を向上させる手法は、弟分のプリウスにも採用されているのである。これって、ホイールキャップのこれまでにない活用法である。ちなみに、SAIの16インチホイールに付くタイヤは、205/60R16 92H である。
2009年12 月15日 (火曜日)
植物由来の樹脂製ラジエータータンク
植物は、光合成で大気中からCO2を吸収して育つため、純粋な植物由来の樹脂は焼却処分しても大気中のCO2総量を増やさない。樹脂の原料を石油から植物に変更できれば、製品のライフサイクル全体での環境負荷を大幅に低減できる。・・・そんな発想から≪植物由来の樹脂製品≫が自動車部品のなかで大注目されている。
デンソーがごく最近開発中だと発表したのが、「植物由来樹脂製ラジエータータンク」。
よく知られるようにラジエーターには上下にタンクを持っている。このタンクは一昔前まで金属製だったが、最近はナイロン系の樹脂製。これを植物のヒマ(蓖麻)から抽出した成分を主原料に使用した植物由来製の樹脂タンクにシフト。ラジエーターはエンジンルーム内で使われるため、高い耐熱性と耐久性が求められ、従来だと重量比20%が限度とされた植物性樹脂使用が、デュポンとの協力で、原材料の4割を植物由来樹脂でカバーしている。ラジエータータンク用としての厳しい要求仕様をクリア。より環境負荷の低減に一歩近づいたといえる。ただし、製品化の時期は不明である。
2009年12 月 1日 (火曜日)
目隠しトルクレンチ
 ≪小さなボルトは片手で、中くらいのボルトは両手で、大きなボルトは身体全体で締める≫というのは戦前の機械工学での格言!? つまり大昔は締め付けトルク、という概念がほとんど存在しなかった。存在しても実にアバウトであった。
≪小さなボルトは片手で、中くらいのボルトは両手で、大きなボルトは身体全体で締める≫というのは戦前の機械工学での格言!? つまり大昔は締め付けトルク、という概念がほとんど存在しなかった。存在しても実にアバウトであった。
先日、VWの整備士コンテストを取材したら実に面白い光景に出くわした。
出場選手が目隠しされたトルクレンチ(数値の出る部分をマスキングされた)を使い、事前に締め付けられたボルトの締め付けトルク値を推理せよ、という課題に取り組んでいたのである。トルクレンチはもちろんプリセット型で、規定値になると「カチッ」と音がするタイプ。これを2回試みることで締め付けられているボルトのトルク値を推測するのである。M8とM10の2本のボルトでの課題。選手に混じって筆者もトライさせてもらい、20Nmと40Nmという答えをカンピューターで導き出した。
果たせるかな、正解はそれぞれ13Nmと33Nmであった。ということはふだん筆者は、少し固く締めていることが判明。これってマニアックだが、意外と面白いゲーム。友人に同じように問題を出し合うというのも一興だ。でもあまりやりすぎるといつしか「トルク人間」になる!?
2009年11 月15日 (日曜日)
フルイドフィルムという名の防錆剤
 同じクルマを長く愛したいユーザーにとって一番の大敵はボディの錆である。
同じクルマを長く愛したいユーザーにとって一番の大敵はボディの錆である。
エンジンがもしだめになったら、同機種のエンジンを載せかえればいいが、ボディのあちこちにもし穴が開いた時は、深くため息をつくばかりで、やがて廃車にせざるを得ない!?
そうならないために、錆びやすい個所に防錆剤を吹き付けておくことが得策だ。
手軽に使える防錆剤は市場を見回してもなかなか発見できなかったが、このほどアメリカの老舗ケミカル製品「フルイドフィルム(FLUID FILM)」が登場したので紹介しておこう。
この製品、もともと第2次世界大戦でアメリカ海軍の鋼板防錆剤として開発されたもので、羊毛から抽出されたウール・ワックスを基本素材とした浸透性の防錆・潤滑剤。スペースシャトルの水平尾翼の稼動部にも使われているというから本命なのかもしれない。
エアゾール・タイプと塗布するタイプがあるのだが、使いやすいのはエアゾール・タイプ。酷く錆付いた金属表面にもいきなり吹き付けて効果があるというから、事前処理を施すのが面倒だという向きにも使える。ちなみに、他製品の浸透潤滑剤はエアゾール溶液全体の20~30%ぐらいしか有効成分が含まれていないがフルイドフィルムは重量比73%が有効成分だということもうれしい点だ。もちろん、揮発性有機溶剤などいっさい含まれない環境にやさしい製品だという。
2009年11 月 1日 (日曜日)
ダイハツのKカー燃費改善最前線
 軽自動車に乗っていて、面白くない事実がひとつある。
軽自動車に乗っていて、面白くない事実がひとつある。
小さい割にはガソリンの大食いだということだ。コンパクトカーや大きなクルマと伍して走るわけだから、それなりの運動量(燃料)が必要なのは頭では理解できても、もう少し燃費がよくならないものか?
こうした長年の疑問に終止符をうつエンジンが近々登場する。
ダイハツのe:S(イース)の3気筒エンジン(写真)がそれ。このエンジン第2世代のKFエンジンと呼ばれるもので、12バルブDOHC,排気量660cc 最高出力43KW/7200rpm 最大トルク65Nm/4000rpmといったスペックは驚くべきものではないが、燃費改善率が10%以上。JC08モード燃費で30km/l(10・15モードなら35km/l前後)というからすごい。これは世界初のⅰ-EGRという燃焼室内のイオンで燃焼具合を見てEGR量を緻密の制御する仕組みや樹脂製の電子スロットル、さらにアイドリングストップを組み込むことで達成。このイースというクルマ、価格が80万円以下ともいわれるアフォーダブルカー(手に入れやすいクルマのこと)だ。
ちなみに、ダイハツでは次世代の軽自動車用エコエンジンとして2気筒直噴ターボエンジンがスタンバイ。これは極限までの熱効率を追求と走りのこだわりを持ったエンジンで、従来に比べて30%以上の燃費向上。ハイブリッドカーに迫る燃費性能となるか!?
2009年10 月15日 (木曜日)
旧車オーナーがそっと教えるメンテのコツとは?
 日産本社が横浜に引っ越したのを期におこなわれた日産ヘリテージカーパレードを取材した。ヘリテージとは≪歴史的遺産≫のこと。早い話、日産の旧いクルマや少し旧いクルマ、計100台が一堂に集まったのだ。
日産本社が横浜に引っ越したのを期におこなわれた日産ヘリテージカーパレードを取材した。ヘリテージとは≪歴史的遺産≫のこと。早い話、日産の旧いクルマや少し旧いクルマ、計100台が一堂に集まったのだ。
なかには、74年前につくられたダットサン14型(水冷直列4気筒サイドバルブ・エンジン)という博物館入りがおかしくないクルマもすべて自走でやってきた。このクルマはドアなどが木と鉄でつくられているためリストアにはずいぶん苦労したというエピソードを持つが、そんなことより、オールドカーのオーナーはメンテの達人ぞろい。
年式や程度によりみな微妙にそのメンテの手法は異なるが、あまり旧いクルマになると異口同音に「部品の入手に苦労しています」。「ボディの錆に苦労していますね。防錆剤をドアの裏側などに吹き付けています」あるいは「クルマはとにかくエンジンですから、新車で下ろして5万キロぐらいは走行5000キロごとにエンジンオイルを換えていました。これがよかったようです」「オイルエレメントを交換が楽なカートリッジタイプに変更しています」「一番いいのは毎日日常の足で使うことですかね。そうすると、あれこれ不具合は早く分かり手を打てますから」ちなみに、取材した17台中4台は、日常の足として毎日ほど使っているとのことだった。
2009年10 月 1日 (木曜日)
消耗部品の交換の目安とは?
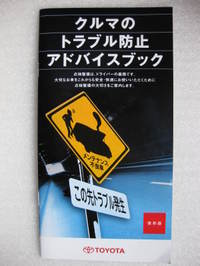 エンジンオイルとオイルフィルターは走行1万5000キロ毎あるいは1年に1回(ターボ車はその半分!)、ブレーキフルードは3年毎、タイミングベルトは10万キロ毎、LLCは3年毎(スーパーLLCと呼ばれるものは8万キロまたは4年毎)・・・・というのはすでに認識している人は多いが、無交換と言われているイリジウムのスパークプラグやブレーキホース、はたまたパワステのホースの正味のところの交換時期の目安となると「うっ!」と言葉に詰まる読者が多いと思う。
エンジンオイルとオイルフィルターは走行1万5000キロ毎あるいは1年に1回(ターボ車はその半分!)、ブレーキフルードは3年毎、タイミングベルトは10万キロ毎、LLCは3年毎(スーパーLLCと呼ばれるものは8万キロまたは4年毎)・・・・というのはすでに認識している人は多いが、無交換と言われているイリジウムのスパークプラグやブレーキホース、はたまたパワステのホースの正味のところの交換時期の目安となると「うっ!」と言葉に詰まる読者が多いと思う。
かくいう筆者も、いろいろ部品メーカーに「おたくで造っている部品の寿命はどのくらいですか?」と聞いて回っても「使われ方でずいぶん違いますから」なんてごまかされる。
そんなとき、面白い資料を発見した。資料というと分厚い文書をイメージするが、ディーラーでユーザーに配布している26ページほどのパンフレット『クルマのトラブル防止アドバイスブック』である。トヨタ自動車の責任編集で、その内容の信憑性は高い。それによると、イリジウムのスパークプラグの交換時期は20万キロ。ブレーキホースの交換時期は20万キロまたは15年だという。パワステのゴムホースもブレーキホース同様に20万キロまたは15年である。ただし、これは平成20年4月1日以降のクルマの限るという。長くクルマを乗ろうというユーザーにはよき目安である。
2009年9 月15日 (火曜日)
静音タイプの家庭用高圧洗浄機に注目
 高圧洗浄機で汚れたクルマを洗う。とくに塩水がかかった下回りの洗浄には高圧洗浄機は最高の使い勝手である。洗車だけでなく、家の外壁の清掃や庭の石やコンクリートにこびりついた苔(こけ)落とし作業などに威力を発揮する。
高圧洗浄機で汚れたクルマを洗う。とくに塩水がかかった下回りの洗浄には高圧洗浄機は最高の使い勝手である。洗車だけでなく、家の外壁の清掃や庭の石やコンクリートにこびりついた苔(こけ)落とし作業などに威力を発揮する。
ところが、この高圧洗浄機、ともすれば音がすさまじく、隣を気にするあまり使うのも控え勝ち。そんな声にこたえて、従来よりも「体感音半分!」という静音タイプの高圧洗浄機が登場した。ケルヒャーのK400というのがそれ。家庭用の洗浄機としては世界初の水冷式モーターを内蔵しているため、モーター音が静かで、しかもモーターの寿命も長くなっているとのこと。
電源は単相100V,消費電力1350W、常用吐出圧力2~7.5MPa,常用吐出水量360リッター/h、本体重量11.6㎏、寸法長さ334ミリ、幅333ミリ、高さ837ミリ、電源コード5メートル。定格連続使用時間は1時間・・・というのがおもなスペック。http://www.karcher.co.jp
« 前 | 次 »
Copyright © 2006-2010 showa-metal .co.,Ltd All Rights Reserved.

