2009年4 月15日 (水曜日)
旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 第12回
 東洋工業の4輪車進出計画は、昭和12年にさかのぼる。
東洋工業の4輪車進出計画は、昭和12年にさかのぼる。
このときは戦時体制へのシフトで軍需生産強化やむなしの事情があり、計画を中断。戦後、昭和25年6月からCA型小型四輪トラック(空冷2気筒1157㏄OHV,32馬力・ジープタイプの1トン積み)が生産開始、30年9月のCF型小型四輪消防車の生産中止まで、四輪車の生産が続いていた。ところが、この6年間にわたる4輪車生産は、実は合計でわずか106台と量産とは程遠い。3輪トラックの生産拡大期とバッティングしたため、4輪車へのまなざしが小さかった。
3輪トラックで蓄積した技術をもとに東洋工業が、戦後の4輪車への新たな本格的なチャレンジをしたのは昭和31年秋ごろだった。2年後の昭和33年4月、DMA型小型四輪トラック「ロンパー」の発売に踏み切った。ユーモラスな「ロンパー」という名称は、"軽快に走る"という意味が込められたペットネーム。セミオーバー型1トン積み。新開発の水冷1105㏄2気筒OHVエンジンを載せ、32.5馬力、3人乗り。3輪トラックの特徴である酷使に耐え、小回りができる四輪トラックとして好評を博し、生産3ヵ月後の7月には、目標の月産500台に到達している。
この成功をふまえロンパーの第2弾というべき1.75トン積みのDHA型車を発売。これはエンジンを1400㏄42馬力で、ひとまわり大きく、荷台に3方開きタイプが加わった。翌34年にはD1100,D1500を世に送り出している。D1100は水冷4気筒1139㏄OHVで、46馬力の1トン積み。D1500は、1.75トン積みで1484㏄、60馬力。
当時の小型四輪トラックの水冷エンジンはサイドバルブ方式が主流だったことを思えば東洋工業のエンジンづくりは半歩から1歩抜きんでていたといえる。この背景には、シリンダーブロック、シリンダーヘッド、クランクシャフトのエンジン主要3部品をシェルモード法による精密鋳造で作られたことによる。とくに昭和34年10月以降はカナディアン・ニッケル・プロダクツ社との技術提携によって、それまでの鍛造品でつくられていたクランクシャフトに、ダクタイル鋳鉄のシェルモード鋳物が用いられた。これは業界他社に先行した技術だった。
2009年3 月31日 (火曜日)
旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 第11回
 “三丁目の夕日”である昭和30年代は、社会が大きく変化した時代。トラック業界は、小型3輪トラックと小型4輪トラックの競合時代がきて、やがて小型3輪トラック業界の斜陽時代がやってくる。
“三丁目の夕日”である昭和30年代は、社会が大きく変化した時代。トラック業界は、小型3輪トラックと小型4輪トラックの競合時代がきて、やがて小型3輪トラック業界の斜陽時代がやってくる。
この時代、3輪トラック市場をリードしてきた東洋工業の製品は、ろうそくの灯が消える寸前の一瞬の輝きに似た光彩を放った。東洋工業にとって、より理想に近い3輪トラックを目指し、技術の向上がある意味で頂点に達したのである。昭和29年、全モデルが改良され、デザインの統一により、ゆるやかにカーブしたサイドガラスが採用され、視界が良くなった。いまで言うパッケージングが強化された。セルモーターが全車に採用され、油圧タペットも装備。しかもサイドドアが全車に装着され、運転席は幌型からスチール製のキャビンへと改善。安全性と耐天候性が劇的に向上したのである。昭和31年になると、業界初の自動強制冷却装置付きのエンジンが装備、バイメタルによるサーモスタットファンによる熱維持性の向上、双胴式のキャブレターによる混合気配分の均一化、ブースト(負圧)進角方式によるエンジンの出力向上とドライバビリティ改善など、その後の排ガス技術につながる技術の片鱗がこの頃から登場している。
翌年にはバーハンドルから丸ハンドルタイプの3輪トラックも登場。積載量が1.5~2トンに増加するに伴い、前輪荷重が大きくなる。必然的に操舵力が大きくなり、腕力では間に合わなくなったのがその背景だ。しかも、スタイルもより洗練され、運転席は荷台から完全に独立し、シートも3人掛け(HBR車)、通風の良い3角窓が取り付けられ機能性も向上している。
昭和34年5月には、空冷356cc,300㎏積みのK360軽3輪トラックも発売。これはダイハツのミゼットで大ブームがおきた軽3輪トラック需要のキャッチアップ。昭和35年には7万台を超え、軽4輪トラックの需要となって引き継がれるのである。翌6月には同じスタイルでT600、さらに10月にはHBR車の空冷エンジンが水冷エンジンに載せかえられ、T1100,T1500がデビューする。3輪トラックが斜陽化するなかで、東洋工業は昭和36年において3輪トラックの生産4万5685台と最高の数値をマークし、シェアを80%に伸ばしたのである。
2009年3 月15日 (日曜日)
旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 第10回
 昭和25年以降の3輪トラック業界は、大型化の傾向を示している。
昭和25年以降の3輪トラック業界は、大型化の傾向を示している。
これは25年9月に東洋工業からデビューした1トン積みのCT車で先鞭をつけたからだ。CT車は1157㏄空冷2気筒OHV32馬力。半球型燃焼室を持つOHV。タペットに油圧式の自動アジャスト機構(油圧タペット)を備え、エキゾーストバルブに回転バルブ(カム山とバルブをオフセットによる技術)を採用するなど、熱負荷の大きな排気弁の耐久性を向上させている。ちなみに、半球型という意味では日本初。セルモーターが付けられ、始動性を容易とした。
このCT型3輪トラックは、エンジンだけでなく車体にも革新技術が盛り込まれている。フロントウインドウに安全性の高い合わせガラスを用い、エンジンを取り付けるうえでゴムマウントを採用していた。この新型車に先立ち、25年8月、CT車2台による箱根登坂テストを試みている。コースは小田原―箱根間。1台は1トン積み、もう一台はその倍の2トン積みで、1トン積みのほうは3速ギアで20分間を全速力で走り、2トン積み車はセカンドギアで33分間急坂を登るというものだった。見事2台とも期待通りの走りを見せたという。
2年後の昭和27年には、1500ccの2トン積み車が登場。大型化に伴い風防窓の取り付け、運転台の覆い、エンジンの冷却装置の強化がおこなわれ、3輪トラックのイメージアップにつながり、性能的にも価格のうえからも小型4輪トラックとの競合関係が生まれてきた時代でもあった。
東洋工業は、昭和27年小型4輪乗用車の本格生産にシフトするのだが、2年前の昭和25年4月、今では過渡的乗り昭和25年以降の3輪トラック業界は、大型化の傾向を示している。
これは25年9月に東洋工業からデビューした1トン積みのCT車で先鞭をつけたからだ。CT車は1157㏄空冷2気筒OHV32馬力。半球型燃焼室を持つOHV。タペットに油圧式の自動アジャスト機構(油圧タペット)を備え、エキゾーストバルブに回転バルブ(カム山とバルブをオフセットによる技術)を採用するなど、熱負荷の大きな排気弁の耐久性を向上させている。ちなみに、半球型という意味では日本初。セルモーターが付けられ、始動性を容易とした。
このCT型3輪トラックは、エンジンだけでなく車体にも革新技術が盛り込まれている。フロントウインドウに安全性の高い合わせガラスを用い、エンジンを取り付けるうえでゴムマウントを採用していた。この新型車に先立ち、25年8月、CT車2台による箱根登坂テストを試みている。コースは小田原―箱根間。1台は1トン積み、もう一台はその倍の2トン積みで、1トン積みのほうは3速ギアで20分間を全速力で走り、2トン積み車はセカンドギアで33分間急坂を登るというものだった。見事2台とも期待通りの走りを見せたという。
2年後の昭和27年には、1500ccの2トン積み車が登場。大型化に伴い風防窓の取り付け、運転台の覆い、エンジンの冷却装置の強化がおこなわれ、3輪トラックのイメージアップにつながり、性能的にも価格のうえからも小型4輪トラックとの競合関係が生まれてきた時代でもあった。
東洋工業は、昭和27年小型4輪乗用車の本格生産にシフトするのだが、2年前の昭和25年4月、今では過渡的乗り物ともいえる「3輪乗用車」を世に送り出している。PB車(写真)がそれで、排気量701㏄,4人乗りで終戦後の一時期東京や大阪などの都市で市民の足として親しまれた「輪タク(自転車タクシー)」に替わるものとして、それなりの普及を見せた。最盛期の昭和26年には年間1000台を超えたという。広島市内でも当時「90円均一タクシー」として親しまれた。ちなみに、この3輪乗用車は、昭和27年、690台をもって生産終了している。
2009年2 月28日 (土曜日)
旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 第9回
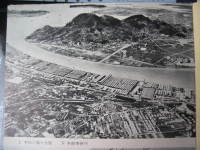 昭和20年8月6日、広島に落とされた原爆は莫大な人的被害だけでなく、多くの建物などに壊滅的な被害をもたらした。
昭和20年8月6日、広島に落とされた原爆は莫大な人的被害だけでなく、多くの建物などに壊滅的な被害をもたらした。
だが幸いなことに東洋工業の建物や設備は、広島の中心街とは小さな山に隔てられていたことから、被害は軽微にとどまった。8月20日、市内にあった広島県庁が、東洋工業の本館や工員更衣室数棟に引っ越し、これを皮切りに裁判所、広島控訴院の司法官庁、NHK広島放送局、中国新聞などが社内の遊休建物に入居し、東洋工業は一時、≪広島の霞が関≫の様相を呈した。
昭和20年12月に生産を再開した背景には、生産財である3輪トラックは昭和12年を境にして戦争終結時まで生産が限りなくゼロになる。当時動いていたトラックは、すでに寿命が尽きた代物ばかり。だが、3輪トラックを生産しようにも原料が素材の入手がおぼつかず思うに任せなかった。次々に製品を世に出せば羽根が生えたように売れることはわかりきってはいたが、肝心の鉄などの素材が手に入らない。
資材は、昭和24年末までGHQ(連合国総司令部)の指示による国家統制のもとにおかれた。そのため、鉄板割当量には限りがあり、自由に大量生産ができるわけではなかった。たとえば昭和22年の鉄板の割当量は、生産実績の3分の1程度。
この鉄板の不足をいわゆる戦後の隠退蔵物資や旧軍施設の払い下げで充当していた。旧海軍で使用していた燃料タンクの鉄資材1100トンとか、徳山燃料廠からの燃料タンク2000トンなどである。払い下げの燃料タンクを工員が溶接機などで展開し、トラックのフレームなどの素材に流用したのである。リサイクル性が高い鉄は、不自由ながらも何とかなった。(あまり知られていないが、昭和33年に完成した東京タワーの一部も、実は米軍から放出された戦車や軍用トラックの鉄素材を活用して建てられている)
鉄素材はなんとか間に合ったが、タイヤが入手できない事態があった。当維持の写真を見ると「足なしクルマ」という奇妙なものが並んでいる。工場の隅に在庫していた3輪トラックの中にタイヤの入庫がままならず、タイヤなしのトラックが置かれていたのだ。ゴムは輸入に頼るしかなく、リサイクルもできない素材。ゴムもGHQによる厳重な貿易統制対象物であったからだ。いずれにしろ、そんな混沌のなかにも希望の火が見えていた時代だった。
2009年2 月14日 (土曜日)
旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 第8回
 3輪トラックメーカーの地位を確立した東洋工業。社長の松田重次郎は、かねてより4輪車計画を立てており、乗用車を含めた3輪・4輪自動車の総合メーカーに発展させる野心を抱いていた。すでに鮎川義介の率いる日産が、昭和10年横浜にダットサンの一貫工場を完成し、フォードとシボレーの輸入車全盛時代に割って入るかたちで、日本初の小型乗用車の量産を成功させていた。
3輪トラックメーカーの地位を確立した東洋工業。社長の松田重次郎は、かねてより4輪車計画を立てており、乗用車を含めた3輪・4輪自動車の総合メーカーに発展させる野心を抱いていた。すでに鮎川義介の率いる日産が、昭和10年横浜にダットサンの一貫工場を完成し、フォードとシボレーの輸入車全盛時代に割って入るかたちで、日本初の小型乗用車の量産を成功させていた。
東洋工業が、小型4輪車の生産を視野に入れた計画に着手したのが昭和11年の末だった。翌12年4月にイギリスのオースチン・セブン(750㏄)を購入する一方、4輪車開発担当技師・竹林清三を工作機械購入の目的でアメリカに派遣。庶民がクルマを軸とした生活を営むアメリカのモータリゼーションを肌で感じさせている。デトロイトの自動車工場を視察、4輪車生産のための参考資料を入手するのも竹林の使命だった。昭和13年にはドイツのオペル37年式(1100CC),イギリスのMG37年式を購入し、リサーチと研究をスタートさせた。
乗用車製造には、3輪トラックにはない工作機械も必要となる。竹林をアメリカに派遣させた目的のひとつもまさにそこにあったのだが、投資した額は当時の金額で約55万円。55万円と聞いてもピンとこないが、当時の家賃が約13円だったというから、ここからアバウトに換算すると、ざっと見積もって100億円ほどだと考えられる。購入した工作機械は…プラット&ホイットニー社のケラーマシン(自働形彫盤)、グリーソン社の捻じれ傘歯歯車歯切り盤、フェロース社製の小型歯車歯切り盤、レーベ社製のカムシャフト盤など。
ところが、こうした4輪車生産の着手しはじめていたところ、暗雲が垂れ始めた。中国との戦争(日中戦争)が始まり、東洋工業は陸軍から命令された小銃の大量生産(写真は小銃工場)と軍需工場向けの工作機械の生産に専念せざるを得なくなったのだ。しかも戦時社会になるに従い、統制経済がしかれ徐々に民生用の資源や物資が自由に手に入らず、昭和15年に小型乗用車の試作が終わった時にはすでに乗用車生産の見通しが立てられなくなり、3輪トラックの生産自体も昭和12年に年間3000台をピークに、太平洋戦争が始まった昭和18年後半より断続的となり、19年には104台、敗戦の年の昭和20年には69台に落ち込んだ。
やむなく、重次郎たちの夢は戦後へ持ち越すことになるのである。
2009年1 月31日 (土曜日)
旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 第7回
 実は東洋工業には、コルクの製造、工作機械の生産、3輪トラックへのチャレンジのほかに、もうひとつ見落としてはいけない業種をそのころスタートさせていた。削岩機(さくがんき)である。
実は東洋工業には、コルクの製造、工作機械の生産、3輪トラックへのチャレンジのほかに、もうひとつ見落としてはいけない業種をそのころスタートさせていた。削岩機(さくがんき)である。
ダムや水路の建設になくてはならない道具である。東洋工業の削岩機の生産は昭和10年。満州事変以来の財政膨張政策による公共土木事業の活発化、軍関係施設、道路、鉄道、トンネルなどの建設、石炭の増産などを背景に削岩機の需要が高まっていた。ところが、当時の国内の削岩機メーカーは、3輪トラックの勃興期同様、町工場的なものが多く、削岩機本来の要求である精密度と、部品の消耗度の激しさ、つまり信頼耐久性に対応できないでいた。
この削岩機業界への進出は、東洋工業の役員の一人で株主でもあった日産窒素肥料(現・チッソ)を中核とする日窒の総帥・野口遵(のぐち・したがう:1873-1944年)のアドバイスから始まった。余談だが、野口は、戦前活躍した実業家の一人で、明治41年に日本窒素肥料を設立したのをはじめのちに中国電力となる広島電灯、旭化成となる日本ベンベルグ絹糸、ホテルロッテとなる半島ホテルを開くなど、電気化学工業の父、朝鮮半島の事業王と呼ばれる。朝鮮半島に大規模な水力発電所を作り、巨大コンビナートを増設した立志伝中の人物だ。
東洋工業の削岩機づくりも、3輪トラックづくりの時に当時名機とされたイギリスの単車を分解し研究したのと同様、削岩機の世界では世界的名声を博していたアメリカのインガソルランドの製品を手に入れ、分解し、各部品をスケッチするなどとことん研究し尽くしている。とはいえ削岩機の心臓部であるピストンの素材の焼き入れにはかなり苦心したと伝えられる。3輪トラックづくりと削岩機のモノ作りに共通しているものがあり、困難を乗り越え、市場で認められる製品と成長していった。
2009年1 月15日 (木曜日)
旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 第6回
 マツダの前身である東洋工業は、昭和5年(1930年)、広島県安芸郡府中村(現・府中町)に約3万3000㎡の土地を取得、3輪トラックの新工場としてスタートしている。
マツダの前身である東洋工業は、昭和5年(1930年)、広島県安芸郡府中村(現・府中町)に約3万3000㎡の土地を取得、3輪トラックの新工場としてスタートしている。
新工場ができた昭和6年にはわずか66台だった3輪トラックは、翌年には518台、さらにその次の年には1251台とうなぎのぼりの生産となった。当時の3輪トラックのタンクには三菱のスリーダイヤモンドとMAZDA(マツダ)のロゴが重なっている(写真)。販売を三菱商事に委託していたためスリーダイヤモンドが記されていた。もうひとつは、MAZDAは社長の姓である松田という意味だけでなく、紀元前6世紀に誕生し、古代ペルシャの国教として栄えた拝火教(ゾロアスター教)の光の神「アウラ・マツダ(Ahura Mazda)の神話にのせて、新しく誕生した“マツダ号を小型自動車界の光明たらしめよう”との願いが込められていた。
東洋工業は、その後2重フレームタイプのDB型3輪トラック、排気量を482ccから485㏄に高めたDC型を昭和9年1月に発売。同年10月には、エンジンの排気量を654ccにアップし、しかもエンジンとトランスミッションを一体型にしたKA型3輪トラックをデビュー。このKA型は伝動装置にすべてギアを使った画期的なものだった。
その後昭和11年までに、TSC型、KC型と次々に改良版を世に送り出し第二次世界大戦前における3輪トラック市場の地歩を確実なものとしている。なかでもモダンなデザインと当時言われたKC型は、昭和10年から昭和13年の2年8カ月の生産期間に5595台という記録を作った。
この時代、東洋工業は宣伝活動にも積極的に取り組んでいる。昭和11年に行われた「鹿児島―東京間キャラバン宣伝」もそのひとつ。マツダKC型4台とマツダDC型1台で、鹿児島をスタートに東京までの約2700㎞を25日間かけて走破。この3輪トラック初の試みで、マツダの製品の優秀性を大いにアピールした。
昭和13年4月に登場したGA型3輪トラックは、計器盤を緑色に統一した「グリーン・パネル」で人気を博した。このGA型に搭載されたエンジンは669㏄で、従来の3段トランスミッションから4段に変更し、登坂力、加速力、燃料消費などあらゆる面で向上したという。
ちなみに、排気量654ccにボリュームアップした背景は、昭和8年8月自動車取締令が改正され、3輪車を含む小型自動車の範囲が排気量750㏄までに拡大されたことによる。
当時マツダの3輪トラックのライバルだったのは、明治40年代に国産初の内燃機関である吸入ガス発動機を作った発動機製造のダイハツ号(昭和5年12月デビュー)だった。発動機製造は、のちのダイハツとダイハツディーゼルのルーツで、ダイハツ号というのは「大阪にある発動機製造」からきた愛称である。戦前の日本では、このように3輪のモータリゼーションが始まっていたのである。
2008年12 月31日 (水曜日)
旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 第5回
 「旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 第5回」
「旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 第5回」
東洋工業は、のちに社長となる息子の松田恒次(つねじ)などの市場調査を踏まえ昭和5年に3輪トラックの設計に着手。その頃の3輪トラック業界は、ウェルビー号の独壇場の時代だった。ウェルビー号というのは、空冷4サイクル単気筒350㏄イギリス製JAPエンジンを搭載し、前進3段の変速機から電装品に至るまですべての部品を輸入品でカバーしていた。しかも車体は、鋼管をガス溶接でつなげた自転車組み立て方式をそのまま使い、ドライブトレインもバイクと同じチェーンドライブ。走行中、フレームの溶接が外れ走行不能になったり、コーナリングが左右で異なるフィーリングを与えるなど現在でいう欠陥の多い3輪車だった。
だが、これでも当時としては、進んでいた。というのは、ウェルビー号が登場する前までの3輪トラックといえば、荷台が前方の「フロントカー方式」(前2輪、後ろ1輪)だったので、これから見れば操縦安定性もお話にならないほど向上したのである。しかも、「リアカー方式」(前1輪、後ろ2輪)になったことで、フロントカー方式より50%も積載量を増やすことができたのである。
設計技師の竹林らの狙いは、こうしたユーザーの不満点を解消し、免許なしでも乗れ、ライバルたちよりも性能が高く最大容積の3輪トラックを作り上げることだった。エンジンはもとより、部品もできる限り国産化することで、一貫的な生産を可能とするなどの点におかれた。設計・試作にあたってはイギリス製JAPエンジン、トランスミッションはやはりイギリスのバーマン社のものをモデルにしている。車体は、当時乗用車やトラック、郵便車として少数輸入され活躍していたドイツのDKW社製3輪車のフレームを参考にしている。
こうして昭和5年秋にようやくマツダ3輪トラックの試作車が完成。
この試作車には東洋工業特許による直線操作式後退付き変速機(リバース機構を持ったトランスミッション)や後車軸差動装置(リアデフのこと)、それにシャフトドライブ方式を採用。むろんエンジンも自前で作り上げている。こうした主要部品を自らの手で作り上げ、しかも素材、設備、工作法などの技術を同時に確立し、量産へのめども立てたのである。このことは、日本の3輪トラック史上画期的な事件だけでなく、のちの4輪製造につながる技術となる。
2008年12 月15日 (月曜日)
旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 第4回
当時の自動車製造を振り返ってみると、ひとことで言うと幼稚というか“か細い”ものでしかなかった。確かに、明治40年に国産初のガソリン車タクリー号が完成してはいたし、明治44年に橋本増治郎が快進社をおこし小型乗用車の脱兎号を作るなどしていたが、いずれもヒト・モノ・カネのいずれかが不足した。舶来品信仰で国産工業製品への信頼性が低かったなどで、苦難に満ちたものだった。量産には程遠かったのだ。
だが、関東大震災を契機に、東京市にT型フォードトラックを改造したバスが走り、大正13年にはフォードが横浜に、昭和2年にはGMが大阪にノックダウン工場を立ち上げた。またたく間にモータリゼーションの前夜とも言っていい状況が出来上がったのだ。
世に言うフォードとシボレーの時代だった。昭和4年の末、重次郎の息子で公務係社員の松田恒次(つねじ:のちの社長)と自動車製作担当技師の竹林清三(たけばやし・せいぞう)の2人が、3輪トラックを開発するため関東と関西に市場調査をおこなったのだが、その年、昭和4年の自動車供給データを見ると、輸入組み立て車数が2万9338台、輸入完成車数5018台に比べ国産車数はわずか437台に過ぎなかった。
大正7年に日本の自動車産業を育成する手段として「軍用自動車保護法」なる法律ができた。これは、政府は助成金を出すことで軍用自動車の基礎となるべき4輪トラックの国産化を促進しようとした。橋本増治郎の快進社などもこの補助法の適用を受けたにもかかわらず、価格面で輸入車と太刀打ちできず次第にフェイドアウトしていった。
量産体制のもとで廉価で丈夫なアメリカ車が日本の自動車市場を支配していたのである。
2008年12 月 1日 (月曜日)
旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 第3回
1920年(大正9年)に創業された東洋コルク工業の社長に就任している。昭和2年である。当時東洋コルク工業は、不況下の中で苦しんでいた。重次郎は東洋工業を立て直す役目を担っていたのである。重次郎は熱いモノづくりの好奇心をこのコルクにも注ぎ、コルクの表面を焼くことで強度を高めることを見出し、高品質の製品を生み出した。だが、コルクだけでは重次郎のたぎる思いをいやすことはできない。
重次郎が目指したものは、機械工作部門と3輪トラック部門だった。
昭和4年1月に東洋工業は、呉海軍工廠と佐世保海軍工廠の指定工場となっている。2年前から、クラウゼ社製の旋盤、ヒューレ製の万能フライス盤、アルフレッド・ハーバード社製のタレット旋盤、シンシナティ・ミリングマシン社製の立てフライス盤、万能工具研削盤、ライネッカー社製のかさ歯車形削盤などの輸入機械、国産工作機械数十台を導入した。一方コルク部門から機械部門へ従業員の配置転換を行うなどし、着々とモノづくりの体制を構築していたのである。
今や歴史の襞に隠れて見えなくなりつつあるが、東洋工業の自動車部門への進出は、2輪車からスタートしているのである。昭和の初頭にイギリス製のバイク2台(フランシス・バーベット号とダネルト号)をサンプル輸入し、各部を分解して部品を一つずつスケッチ、試作につなげた。昭和4年11月に2サイクル250㏄エンジンを完成し、翌5年3月には完成車の試作にこぎつけた。
試作したのは計6台で、その1台が広島市の招魂祭の余興としておこなわれたオートレースで当時名車の誉れ高かったイギリスのアリエルを抑え、初優勝を飾ったほどだ。このバイクは、計30台製作され、1台350円~380円で市販している。現在の貨幣価値に直すと270~300万円といったところだ。
2輪製作は、このときが最初で最後だった。重次郎は、より普遍性と将来性の高い3輪トラックに目を向けたのである。大正の末から昭和の初めにかけては、馬車や荷車が物流の主役だったが、3輪トラックが主に中小企業の貨物運搬手段として急速に広まる可能性を見て取ったのだ。
« 前 | 次 »
Copyright © 2006-2010 showa-metal .co.,Ltd All Rights Reserved.



