2008年1 月15日 (火曜日)
クルマの一生のうちCO2の発生は走行中が78%
 日本全体のCO2排出量は年間約12億8500トン(うち輸送関係は約20%!)。これを減らすのが急務なのはなんとなく理解しているのだが、ではどうすればいいのか?
日本全体のCO2排出量は年間約12億8500トン(うち輸送関係は約20%!)。これを減らすのが急務なのはなんとなく理解しているのだが、ではどうすればいいのか?
まず自分のクルマの一生分のCO2発生はどんな具合なのか? これを知っておこう。
クルマの一生は、原材料(13%)→製造(5%)→輸送(0.8%)→サービス(3%)→走行(78%)→廃棄(0.2%)という具合。つまり≪走行中がクルマ一生の78%のCO2を発生している時期≫となる。
となるとやはり、燃費のいいクルマに乗り換えるのもひとつだが、いま乗っているクルマを燃費重視で扱うことの大切さが身に沁みる!? 具体的には、急発進・急停止はしない、アクセルを緩やかに踏む、無駄な荷物を載せない、計画的にドライブしてなるべく走行キロ数を短くする、タイヤの空気圧をこまめにチェックする。といったエコカーライフに徹する。これだけで積もり積もって、10~15%の燃費節約、CO2発生削減につながるという。
2008年1 月 5日 (土曜日)
廃タイヤの活用法
 あまり知られていないが、日本列島で年間に使用済みとなるタイヤは人口とほぼ同じ1億3000本だ。うち大半はチップ状にされセメント工場などの熱源として第2の人生を送る。これをサーマルリサイクルと呼んでいるのだが、2~3割は実はマテリアルリサイクルという道を歩んでいる。
あまり知られていないが、日本列島で年間に使用済みとなるタイヤは人口とほぼ同じ1億3000本だ。うち大半はチップ状にされセメント工場などの熱源として第2の人生を送る。これをサーマルリサイクルと呼んでいるのだが、2~3割は実はマテリアルリサイクルという道を歩んでいる。
そのうちのひとつが、舗装路面に姿を変えること。正確に言うと「多孔質弾性舗装材」である。
廃タイヤをまず、チップ状にして滑り止めの鉱物やウレタン樹脂系のバインダー(接着剤)を混ぜ合わせ、路面に施工するのだが、夏場は数時間で固まるのだが、冬場が半日待たなくてはいけないというのが、ひとつの課題だという。
技術的にはかなり完成度が高く、こうして作った舗装路は内部に空隙があるためノイズとバイブレーションが減少し、まわりの住居への騒音被害が小さくなるため、遮音壁が不要となり、ひいては見通しがよくなり安全にもつながるという。弾性があるので、冬場凍結した氷が割れやすいというメリットもあるという。
ただし、コストはアスファルトに比べると数倍もかかり、実はこれが最大の課題。
付け足し情報としては、バス・トラックの使用済みタイヤの一部は、トレッド部を張り替えた再生タイヤ(更生タイヤともいう)というのがあり、路線バスの後輪などに使われている。
2007年12 月15日 (土曜日)
軽自動車1台をつくるのに約530kgの鉄
 マスコミなどで知られているように、工業製品をつくるうえで欠かせない「素材」が高騰している。中国の急速な経済成長などがその背景にあるようだ。資源を海外に頼っている日本を考えると、不安が頭をよぎる。
マスコミなどで知られているように、工業製品をつくるうえで欠かせない「素材」が高騰している。中国の急速な経済成長などがその背景にあるようだ。資源を海外に頼っている日本を考えると、不安が頭をよぎる。
自動車の素材といえばまず思い浮かぶのは≪鉄≫である。その鉄はクルマ一台にどのくらい使われているかというと、軽自動車でいえば約530㎏。その原料となる鉄鉱石はその約1.4倍なので741.7㎏ということだ。この数字で驚いてはいけない。アルミはもっとすごい。軽自動車1台にアルミは46.2kg使われている(エンジンやトランスミッションなど)。これを1円玉に換算すると4万6200個。つまり4万6200円分となる!? その原材料であるボーキサイトはその4倍なので184.8kgが必要となる。
銅はどうか? 軽自動車1台に銅の使用量は6.2kgといわれる。10年玉(1枚4.5g)は銅でできているので、約1377個分、つまり1万3770円分。この銅をつくる原料の銅鉱石に換算すると100倍の616㎏となる。ガラスもクルマには使われている。軽自動車でいえば約29㎏。これは牛乳瓶で約120本分なのである。
素材からクルマを眺めてみるのも面白い。
2007年12 月 1日 (土曜日)
日本の自動車メーカーのさび対策の不思議発見?
防錆鋼板というクルマのボディの鋼板をご存知だろうか?
通常の鋼板のうえに亜鉛メッキをして防錆力をうんと高くしたものだ。ところが、この防錆鋼板は価格が通常の鋼板より2割ほど高いので、ただでさえ材料高騰のおりできれば使いたくないのが自動車メーカーの本音。冬場に融雪剤をまかない地域なら、8年~10年はまず錆びることがないので、「防錆鋼板」を敬遠したいメーカーも出てくる。
仕向け地(海外)では、日本より錆びやすい環境があり、使い分けをしているメーカーもある。ズバリ、日産とホンダがこのコンセプト。この2メーカーは、日本仕様は防錆鋼板をあまり積極採用していない。逆にトヨタや三菱は地域に関係なくオールコンディション仕様。つまり値段の張る防錆鋼板を分け隔てなく使っている。
日本での融雪剤の塗布する地域は東北と北海道で全体の約3割。この3割をどう考えるかということらしい。サビ対策は8年後~12年後で、あるいは15年近くたたないと明確にその効果が見えない≪性能≫である。6~7年で乗り換えるユーザーには関係のない話しかもしれないが、10年~15年間同じクルマに乗り続けたい人は知っておいて損はない情報といえる。
2007年11 月15日 (木曜日)
来年続々登場する!?クリーンディーゼル乗用車
 来年あたりにクルマを乗り換えようと考えている読者は、いつにも増してたぶん頭を悩ませそうだ。
来年あたりにクルマを乗り換えようと考えている読者は、いつにも増してたぶん頭を悩ませそうだ。
燃料電池車は少し先になるとして、クリーンディーゼルエンジン乗用車が続々デビューする見込みだからだ。いまやディーゼル乗用車は欧州では乗用車販売の約半分。かつての≪臭い・トロイ(走りがのろい)・うるさい≫の3大悪の代名詞だったディーゼルがハイテク技術(コモンレール噴射、電子制御などの合わせワザ)で別人格ともいえるほどいいクルマになって蘇ったからだ。
あれほどディーゼルの悪口を言った石原都知事は、前言を取り消す時期に来ているのであるが、政治家という存在は悔い改めることは政治生命を失くすことぐらいに考えているらしく、たぶんそれはしないだろう!?
それはともかく、今回のモーターショーではマツダ、ホンダ、三菱、スバルなどがディーゼルエンジンを展示した。トヨタと日産はすでにお披露目しているので、ほぼこれで出揃ったことになる。なかでも、三菱の2.2リッターのディーゼル(写真)は、コンプレッサー側にも可変機構を組み込んだターボチャージャーを備える。つまりツインターボチャージャー同等の下から上までのターボ効果を発揮するということだ。このディーゼル情報、おいおいリポートしていきたい。
2007年11 月 1日 (木曜日)
スカイラインクーペーのエンジンに付いたVVEL
 いまどきのエンジンに求められるのはよく知られるように、燃費、軽量化、高レスポンス、排ガス性能の4つだ。
いまどきのエンジンに求められるのはよく知られるように、燃費、軽量化、高レスポンス、排ガス性能の4つだ。
この4つの要求をみごとに実現したメカニズムを、つい最近デビューしたスカイラインクーペの心臓部に採用された。450万円近くもするスカイラインクーペは、艶やかで躍動感のあるスタイリングで中年の心をギュッとつかむところがあるが、今回はエンジンフードの中身の話。
通常のエンジンはアクセルペダルを踏み込むとエンジンのスロットルバルブが開き吸入空気量を増やしそれに見合った量の燃料がインジェクターから噴射する・・・このスロットルバルブのおかげで吸入抵抗(ポンピングロス)が生じ、そのぶん燃費悪化を招いていた。このVVVEL(ブイベル)は、スロットルバルブをほとんど動かすことなく、吸気バルブの開閉で吸入空気量をコントロール。フェイルセイフのためにスロットルバルブを持ってはいるが、たぶん近い将来、このスロットルバルブはなくなる運命だ。
カムシャフトのうえにコントロ-ルシャフトを付け、それを作動するボールスクリュー機構とモーターを備えるため、ヘッドをやや複雑に作り変えなくてはいけない。エンジン自体も約10キロ重くなる。でも、CO2は10%低減でき、出力向上するし、燃費も高まる。
2007年10 月15日 (月曜日)
単筒式ショックアブソーバー
 クルマの足回り部品のひとつであるショックアブソーバー。走行中スプリングが受けた衝撃によって発生する固有振動を吸収し、振動をはやく減衰させて乗り心地をよくする・・・というのがショックアブソーバーの役目。この部品とセットで登場する「減衰力」という言葉は、スプリングの動きを抑える力のことだ。
クルマの足回り部品のひとつであるショックアブソーバー。走行中スプリングが受けた衝撃によって発生する固有振動を吸収し、振動をはやく減衰させて乗り心地をよくする・・・というのがショックアブソーバーの役目。この部品とセットで登場する「減衰力」という言葉は、スプリングの動きを抑える力のことだ。
通常のショックアブソーバーは、複筒式と呼ばれるタイプで10㎏/c㎡以下の低圧ガス。日本車は、このタイプが大部分。だが、ベンツやポルシェなどの欧州車では従来から「単筒式ショックアブソーバー」が装着されている。クラウン、セルシオ、三菱のランサーエボリューション、アウトランダーなど、ごく一部の日本のクルマにもこの「単筒式ショックアブソーバー」が装着されはじめた。
単筒式ショックアブソーバーは、複筒式にくらべピストン径が大きくとれ、しかもオイル容量を大きくできるので、ショックアブソーバーとしてのキャパシティが大きく、性能そのものも高い。ガス圧は15~30㎏/c㎡と高い。ケースの真円度を高め、シールも上等なものにしなくてはいけないため製造コストは高くなるが、構造が単純なので、オーバーホールがやりやすく、長期で考えるならコストパフォーマンスが高いともいえる。
ただし構造上フロントのマクファーソンストラットタイプには使えず、フロントならWウッシュボーンタイプで、リアは30ミリほど全長が長くなるため荷室面積を稼ぎたいクルマには不向きだ。
2007年10 月 1日 (月曜日)
侮るなかれ!子供向けフリーBOOK
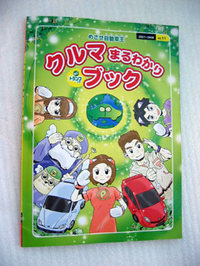 NHKの子供ニュース、TBSの子供電話相談室など子供向け番組は、大人が実は楽しく学べる世界でもある。
NHKの子供ニュース、TBSの子供電話相談室など子供向け番組は、大人が実は楽しく学べる世界でもある。
トヨタが年度版で出している『めざせ自動車王 クルマまるわかりブック』も紙媒体のすぐれものだ。現在小学5年生の社会科では日本の自動車産業がカリキュラムのひとつになっていて、これにそったB5判50ページの小冊子。企業がつくっただけに宣伝臭こそあるものの、大人にも十分読み応えあり、たしかな知識を得ることができる。自動車のリサイクルを4ページにわたり図説。3分でその世界の全貌がつかめるし、難解なクルマづくりの流れも10ページにわたり写真とよく練られた文章のおかげで10分あれば理解できる。クルマ一台は約3万個の部品からできていて、つくるのに大きく分けてプレス、溶接、塗装、組み立て、検査の5つがあり、このあいだ約20時間かかる・・・という文章を読むと目からうろこ状態になる大人がいるはず!? しかも製造ラインで働く人の声がコラムで楽しめるので、立体感で理解できる。
クルマの写真が載っているトランプ付きで、能動的な知的刺激も受けることができる。
この小冊子、小学校や小学生に無料で配布中だ。問い合わせは葉書またはFAX。
〒471-8571 トヨタ自動車広報部「クルマまるわかりブック」係 FAX0565-23-5708
クルマこどもサイト http://www.toyota.co.jp/jp/kids/
2007年9 月15日 (土曜日)
ヘッドライトのメンテナンス
 いつの間にかヘッドライトがガラス製からポリカーボネート(略してPC)と呼ばれる樹脂にシフトした。
いつの間にかヘッドライトがガラス製からポリカーボネート(略してPC)と呼ばれる樹脂にシフトした。
デザインの自由度が向上し、耐衝撃性も多少高くなり、いいこと尽くめ!? と思いきや、ガラス時代にはなかったトラブルもなきにしもあらず。表面のコーティングがはがれ、黄ばんだり、曇りが生じたり。ひどいときには光度が保安基準を満足できないケースもある。経年劣化が原因だ。
そんなときは中古パーツで対応するのもいいが、そうならない前にケミカルでお手入れができる。
ソフト99の「ライトワン」という商品は、2段構えでヘッドライトをメンテする。まずベースクリーナーで表面の汚れや細かい傷を落とし、コーティングを保護する。次にハードトップコートで表面にガラス上の硬質皮膜をコーティングする、というもの。その効果は6ヶ月にわたるという。
このケミカル用品は、ヘッドライトだけでなくテールランプにも使える。
2007年9 月 1日 (土曜日)
ナノの世界は自動車にもある!
 ナノという単位をご存知だろうか?辞書を引くと・・・・10億分の1メートルのこと。
ナノという単位をご存知だろうか?辞書を引くと・・・・10億分の1メートルのこと。
排気ガスを浄化する触媒は、白金などの貴金属。その貴金属の大きさがナノ単位で語られる大きさなのである。
ここからが本題だ。触媒は、アルミナなどの基材と呼ばれるベースの上に貴金属をつけている。ところが使っているうちに熱が加わるなどで貴金属同士がくっつき、加えて基材同士も隣同士が結合し、結果として貴金属の表面積が小さくなり、触媒の働きがダウンする。
従来の機材であるアルミナではなくセリア系にすることで、いっきにこの触媒劣化トラブルを解決することができたというのが、日産のエンジニアの話。従来なら新品時に1ナノ単位だった貴金属が100ナノと巨大になったのだが、この新技術でせいぜい5~6ナノ程度にとどまり、超寿命が維持できるというのだ。
それまでは触媒の劣化を見越して多めに投入していた貴金属を、この技術で半減でき、メンテナンスすることなく12万マイル(北米で)まで保証するまでにいたったという。
空気の浄化とメンテナンス費&コストの削減という話題である。
« 前 | 次 »
Copyright © 2006-2010 showa-metal .co.,Ltd All Rights Reserved.

